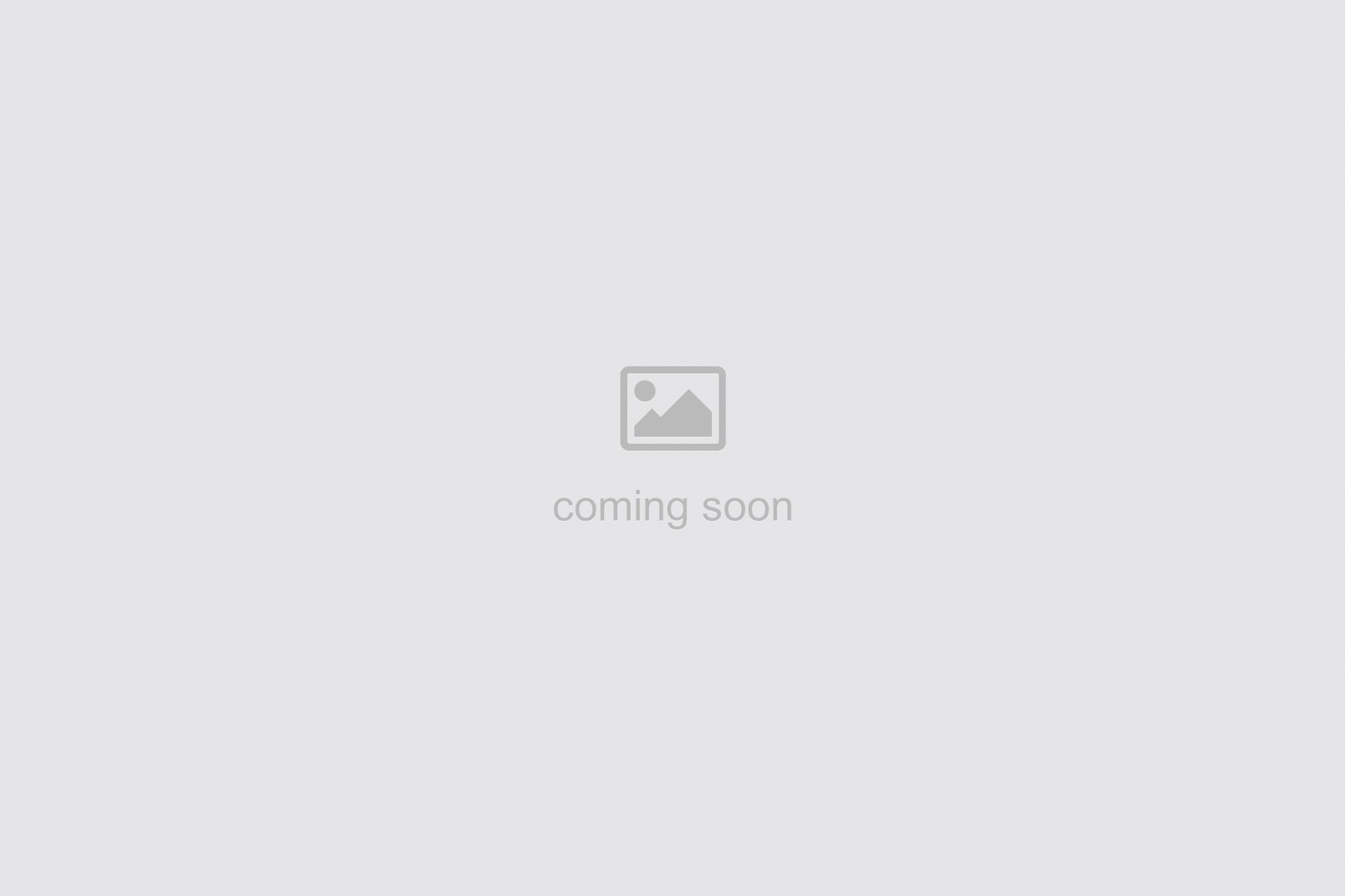2019年1月号(619号)亡き義母との正月
2019-01-01
2019年1月号(619号)
亡き義母との正月
~七十年の彼方の華やぎ~
学園長 吉野 恭治
父は私が10歳のころ再婚した。母が他界して5年ばかり過ぎたころだった。父のその当時の決断のありようを、いまさら聞くすべもない。2月のみぞれの降るような寒い夜に、義母は人力車に乗って嫁入りをして来た。その頃の結婚式は、まだそれぞれの家で行う時代で、母方の親族も何名かが同行してきた。普段は祖母と父と私との3人暮らしだったが、突然にその夜はにぎわった。義母は20代半ばで、初婚だった。
我が家に4人目の家族を迎えたのだが、今まで古風で静かな家が、新しい母ひとりの存在で、華やいだ。かなり記憶のかなたではあるが、その翌年の最初のお正月迎えは、今でもさまざまの記憶が断片のように残っている。台所の板の間にゴザを敷き、祖母と義母と私の3人で餅ばなやお餅を作った。その頃お餅を搗く(つく)というのは2~3人でチームをつくり、民家を巡回して、依頼した家の前で「餅つき」をやるという方法があり、その方法をとる風景も多かった。あらかじめ予約して、もち米を焚き上げる時間を予定して待つのが楽しみだった。つきたての餅の塊を、3人で手早く「餅」にする。そして餅ばなを枝に取り付け、神棚の横に括り付けて飾る。新しく母を迎えた「お正月」の準備は、本当に一つずつが華やいだ楽しさがあった。
街もまた華やいだ。大晦日が近くなると、掃除やガラス拭きなどで、いつもより商店街に人の姿も明かりも遅い時間まで多かった。街自身が活気を産み出すような「活き活き」とした姿が、大晦日の前には続いたものである。神棚に昆布を飾り、お神酒を供え、気持ちのせいだったと思うが、家の中がすっきりと明るく、そうした空気を「お正月の匂い」と考えていた。この匂いには家庭による差があろうし、そのことが「お正月」を家族行事と思わせる原因でもあった。
家庭の主婦は夜は大晦日の数日前から「おせち料理」づくりが始まる。我が家でも祖母オンリーだったおせちが、母を迎えて何種か新鮮味を加え、そこそこ華やいだものである。飾り、掃除、それに調理、すべてがかたづくのは大晦日の、それも夜に近い。義母が嫁いできた当時、まだ「紅白歌合戦」は始まっていない。多くの主婦が台所で耳傾けながら「見た」というより「聴いた」紅白は、第1回のテレビ放送が1953年、昭和28年でそれからのちのテレビの普及率を飲み込んで、「紅白歌合戦」は国民的番組となった。大晦日の主婦としての仕事を一通り片づけて、それから美容室へ出かける。理容室も深夜まで営業を続けたが、美容室は夜明けまでである。義母が早朝4時ごろに帰って来たのを何年か知っている。母が髪に花飾りをつけて、はじめて見るような髪型で帰ってくると、「お正月なんだ」と実感した。それだけでうちの中が華やいだ。考えてみればそれはもう新年である。道路は「初詣で」の人々も多く、義母のように大晦日を引きづりながら、新年の朝を迎える者もいた。銀行も深夜まで明るく、神社の近辺は屋台でにぎわった。
紅白歌合戦が国民的番組になったのは、テレビの普及の進んだ昭和35年、1960年くらいではないか。その頃から次第に「お正月の準備は早い目に済ませて、夜は家族全員が炬燵に入り、テレビを見る大晦日」になっていったように思う。プレ正月とでもいうべき時間で、働き駒のような主婦の姿を変えていったといえるだろう。
この間六本木の、デザインが売りの小物を扱う店に出かけて、お正月飾りを買い求めた。しめ飾りも斬新なデザインのものが多く、数千円以上はする値段から言っても、1年で焼いてしまうというのも困ると迷っていると、販売スタッフの女性が「最近は何年か使われる方がほとんどです。毎年取り換えるなんてなさいません」という。「お正月飾りなんてしないのよという若いお客様も多くなりました」とも聞いた。お正月が荘厳な行事で、どこか神々しいものであった時代は、もう戻らないのではないか。しみじみと回顧と反省を込めて除夜の鐘を聞くこともなくなるのではないか。つまり「お正月の一連の儀式や飾り」は各家庭のプライベートな問題になりつつあるように思える。
つい先日、秋篠宮はご自身の52歳の誕生日の会見で19年11月14日に行われる大嘗祭の費用は国費で賄うのは適当かどうか」と疑問を呈された。こうした行事は皇室のプライベートなものであるという意見で、伝統的な行事も時代とともに変わることはいいことだという意向にもなっている。「残念ながら宮内庁が聞く耳を持たなかった」とまで述べられた秋篠宮の強い批判は、行事すべてを古式豊に行う必要はないというようにも思える。前回、現天皇の即位の際の大嘗祭も、国費であったがおよそ22億円もの費用がかかったという。
庶民のお正月の姿が、大きく様変わりするのは当然であろう。門松を立てる家はほとんどないし、しめを飾らない若い夫婦も増えているという。自家用車にしめをつける家庭もめっきり減った。うらじろなんて知らない人もいるのではないか。羽子板も羽根つきも過去のものとなっている。
おせち料理の変貌にも驚く。定番だった黒豆も栗きんとんも若者に人気がない。数の子はいつの間にか高級食材となっている。山陰ではまだ定着度の高い小豆雑煮も、その甘さゆえに敬遠されつつある。しかも急激にそれらの傾向が進んでいる。
主婦が晦日近くに頑張って作る「おせち」も、一時は冷蔵ものが出回った。たしかにすでに盛り付けて届く「おせち」の便利さはそれなりの価値があった。しかし家族間で料理の好みが異なると、残りものとなる料理もあり、なによりも冷蔵物は保存できる期間が短い。それに輸送中の荷崩れで商品価値の落ちる場合もある。そこで冷凍ものの「おせち」が登場した。好きなものを食べたいときに解凍し、場合によっては1年でも保存できる。今は冷凍の「おせち」が主流という。私が驚いたのは、九州のある一業者で、今年の「冷凍おせち」の受注が、すでに16万個に達しているというすごさである。
新しい母が嫁いできて70年もの歳月が流れた。70年の間に日本の家庭の伝統行事の姿さえ大きく変わった。お正月が襟を正すような期間とは違ってきているのだ。流れるような歳月の中で、小学生だった私は、新妻らしい匂いをたたえたあの頃の母を思い出す。義母が逝きてはや30年、父が逝きて50年、時は無常に流れる。
父が亡くなった時、僧侶が静かに詠ってくれた「ご和讃」に涙が止まらなかった。あれ以来神式であろうと仏式であろうと、人のこころを強く打つものがあることを知るようになった。お正月の儀式の中にもきっとそうしたものが息づいて、時に応じて、やさしく強く、わたくしたちを包んでくれると信じている。