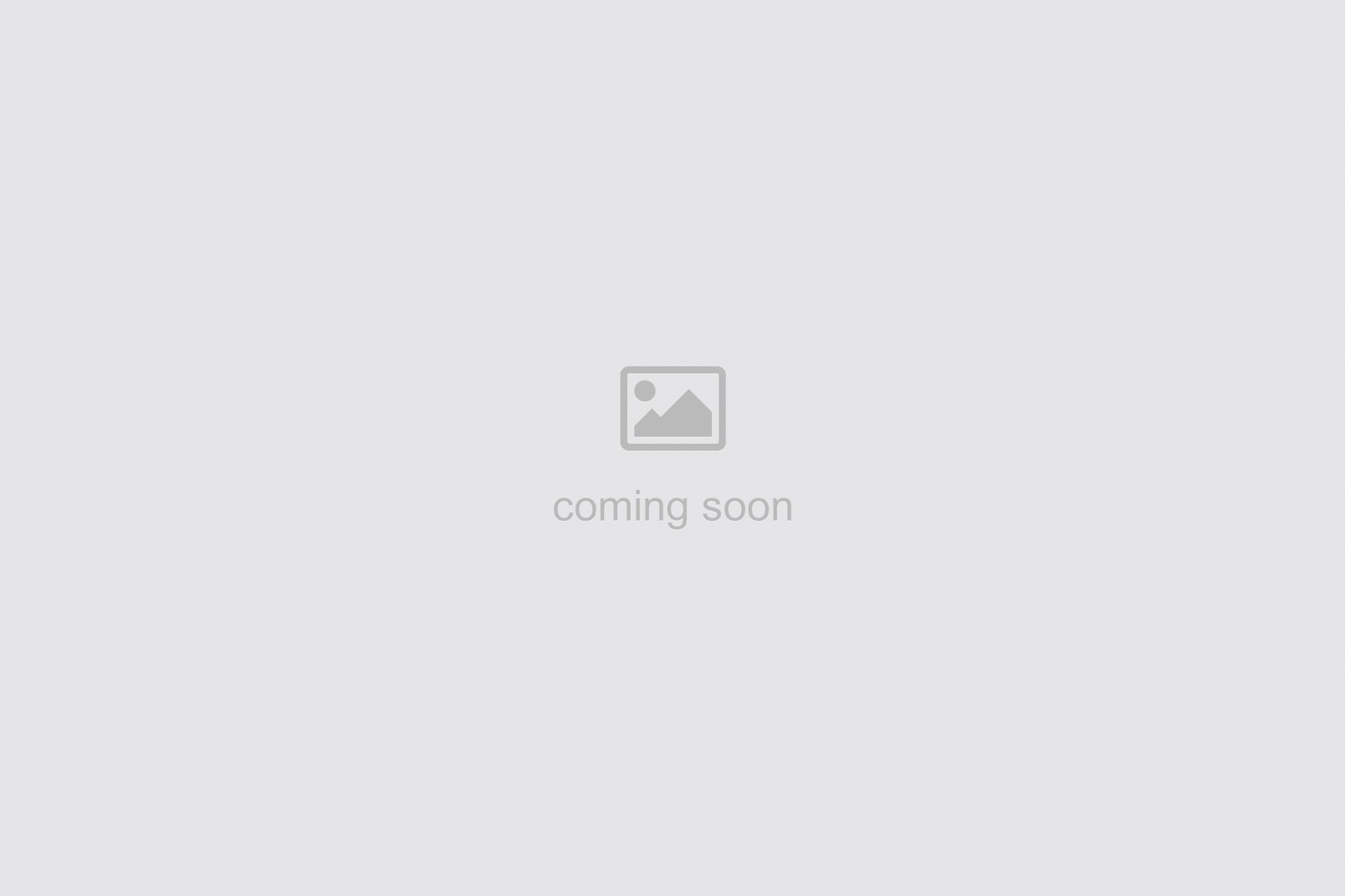2018年5月号(611号) テレビは死んだか~ネット動画の侵攻~
2018-05-01
オススメ
2018年5月号(611号)
テレビは死んだか
~ネット動画の侵攻~
テレビは死んだか
~ネット動画の侵攻~
理事長 吉野 恭治
4月某日の新聞のテレビ欄である。「世界の村で発見!こんなところに日本人」「今夜はナゾトレ 一茂&假屋崎久本、最下位バトル勃発」「火曜サプライズ 興奮広瀬アリス秋葉原めぐり、のびーるチーズづくりと猫カフェ」「踊るさんま御殿 春のモテ美女超満開!」「この差って何ですか?病気のサイン尿の色の差」どれを見ようかと思う前に、胸がつかえるようなゲップの出るような不思議な満足感に襲われる。「もう見なくてもいいや」というものだ。先日BSで「テレビは死んだか」というビートたけしと池上彰の対談番組があった。死んだかどうかという前にビートたけしも死なせた一人であったようにも思えた。テレビは死にかけているかも知れない。今や瀕死の重症だと言っていいのではないか。
70年代から80年代にかけて、若葉では時間割の編成時に、どうしても考えねばならないことがあった。土曜日の夜の講義と木曜日の夜の講義は、その学年の生徒から苦情が多かった。土曜日はドリフターズの「8時だよ!全員集合」、木曜日は黒柳徹子と久米宏の「ザ・ベストテン」が見られない。この両方が見られないということがないように、学年の講義が重ならないように注意したり、受験を控えた中学3年生にその夜の講義が振り当てられたりした。それほどテレビは熱狂的だった。当時は各家庭にビデオなどほとんどない。それに極めて高価だった。しかし今はビデオで見たい時に見れるようになった。でもそれほどまでにしてテレビを見たいという熱狂はもはや子どもたちにはない。そしてその波は確実に大人たちの世代へ感染し始めている。さらに子供たちの成長がこれからテレビ離れの世代を広げているだろう。
最近そのことを強く感じさせることがいくつかあった。ひとつはエッセイストの中野翠さんのエッセイに、「最近はBSに面白いものが多い」というものである。そのうえで、いくつかの興味ある番組を紹介している。前記したビートたけしの対談で、彼は「BSの番組は自由でいい」というようなことを述べている。さまざまの発言規制のある地デジのテレビ番組に比べると、まだBSにはそこまでの制約が課されてはいないということだろうか。たしかにドラマなどでもスポンサーの関連商品の使用やセリフには大きな注意も必要かもしれない。その点でまだスポンサーのほとんどないBSは、そうした制約への神経の使い方が緩やかなのかもしれない。
先日週刊誌でこんな記事を目にした。ある大学教授が小学校の生徒に対して訪問授業にでかけて、その授業の様子をカメラを持ち込んで撮影したという。その時子どもたちが「え、テレビ?何チャンネルで?」と聞く。スタッフの一人が「違うよ。ユーチューブで流すの」と答えると、目を輝かせて反応する子どもが多かったという。「ユーチューブだって!」「ピカキン!」「なんで検索すると見れるの?」と興奮する。今やテレビよりもユーチューブの方が子どもたちに圧倒的に関心も人気も高い。その折にこんな話も載っていた。ローカルのテレビ局では、その地元の県庁から広報番組を受注することは、営業上も。テレビ局の存在感からも極めて大切なものだろう。その県の特性も、細やかな観光資源も、果ては人情までも「絵」にして見せるノウハウがある。しかし今やそうした番組の企画コンペでは、東京など大都市から参入してくるインターネットコンテンツの制作会社に広報番組委託をさらわれることが多くなっているという。考えても見るがいい。遠く県外や国外から観光客を誘致したり、日本の隅々まで特産品を紹介したり、世界中に宿泊施設の紹介ができれば、ネット動画の方がどれだけ魅力的なことだろうか。テレビ局の前にある「明日」は決して明るいものではない。少子化や人口減少におびえる企業や事業と同じく、テレビ局は「テレビ離れ」という社会現象にこのままでは抗しえない。
今政府が検討を進めている放送制度改革は、特別にテレビ放送などという枠組みを止めて、動画配信サービスと同等同系列に扱おうという改革である。これが実現するとテレビ局のステイタスは根底から揺らぐ。また視聴者の側からも、事実を曲げない正しい報道や、できるだけ多くの視点や観点から人々が意見を述べる機会などが失われてゆくことも考えられる。それらはこれまでテレビ局が担ってきたものではないか。
先日「衛星劇場」という映画配信サービスで、「ゼロの焦点」という映画を観た。1961年の制作だから、もう60年近い昔の作品である。原作は松本清張。金沢出張に行ったまま帰らない新婚の夫を待ちきれず、夫の行方を捜し求める鵜原禎子を演じた久我美子も、東京から流れ帰った金沢の煉瓦工場の女子社員田沼久子を演じる有馬稲子もすでに80歳を超えている。西村晃、沢村貞子、加藤嘉など今は亡き名優たちが出ている。この映画はモノクロである。しかし戦後という未曽有の困難の中で進展するドラマと、その舞台となった能登半島の貧しい漁村の風景は、驚嘆に近い感動を呼ぶ。松本清張の着眼もすごい。戦後の混乱を生き抜く女たちの哀しみが、荒涼たる能登金剛の海岸で結末を迎える。いまから60年も前、私たちはこのような素晴らしい映像を見ることができたのである。重厚で吠えるような冬の日本海、娯楽映画だがその映像の重さにたじろぐほどだ。
60年後の今、私たちが日々見せられている画面はどうだろう。極彩色で画面は美しい。しかし私たちはテレビから重厚な感動などを受け取ることがあるのか。来る日も来る日もお笑いタレントがひな壇に並んだ、ほとんど内容のないスタジオ番組を見るしかない日々は、そのままテレビ離れを助長するように思えてならない。TBS系で先日まで「99.9刑事専門弁護士」というドラマがあった。この中の「いただき松任谷由実」などというセリフに最初は笑っても、週を重ねると「いただき松田聖子」に腹立ってくる。その悪ノリにテレビが今毒されている気がする。毎日出てくる司会者のトークに、理性も知性も感じなくなっている。
ある大学教授が大学生にアンケートをとった結果がある。「もし自分が映像制作が得意だったら、①テレビ局の正社員 ➁ユーチューバーのどちらになりたいですか」集計では➁の方が多かった。このことは就職を控えた若い世代にも、働く場としてのテレビ局が敬遠されつつあるということだろう。ドラマだけの問題ではない。日本のこれからを報じるべきテレビニュースを背負う人材も間違いなく育つのかと思いたくなる。ドラマにも報道にもスタジオショーにも、重い課題が重なっている。
生き抜くために「夜の女」に身を落とした女性は今どうしているのだろう、松本清張はその疑問に「ゼロの焦点」の筆を執った。いまテレビは何を焦点に、ゼロからの決意あるスタートを待たれているのか。