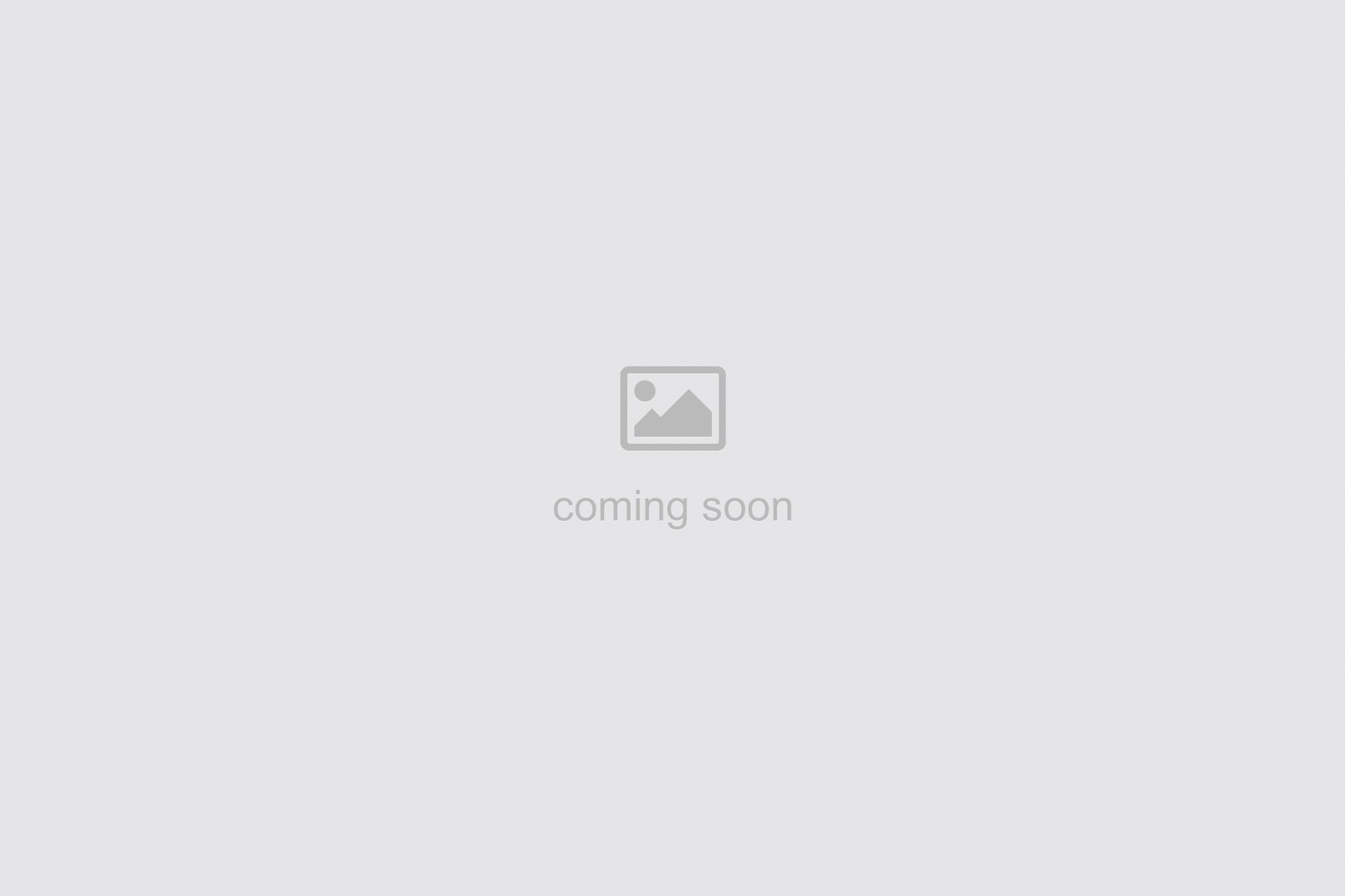2018年1月号(607号) 母校はなくならないか
2018-01-01
2018年1月号(607号)
母校はなくならないか
~閉校の危機に襲われる地方私大~
母校はなくならないか
~閉校の危機に襲われる地方私大~
理事長 吉野 恭治
2017年、全国の18歳人口は120万人である。もっとも18歳人口の多かった66年(昭和41年)で250万人、その後の第2次ベビーブームで92年(平成4年)には200万人。それが今年120万人で、最多期の50%になっているのが衝撃的だが、23年には110万人、31年には100万人割れを予想している。これは今年に比べて20万人もの減少になると予想される。現在大学への進学率はほぼ50%、それだと実に10万人の大学進学者の減少となる計算で、比較的小規模の、1学年定員1000名程度の大学なら、現実的には100校が消滅する計算になる。大学はまさに存続危機に直面しているといわねばならない。
文部省の対応にも確かに問題がある。学生減少期がもうそこに見えているのに、毎年毎年新設大学を認め続けた。地方にも大学新設が続いた。目先の学生の進路処理には有効だったかもしれないが、長期的にみれば早くから大学設置数が過剰になることがわかりきっていた。それが今現実に迫ってきている。今度は抑制に転じなければならない。今年文科省は、東京23区内に私大の新設や増員を認めないという対応を決めた。しかしこれが少子化の対応に効果があるとも思えないし、首都圏への学生集中の歯止めになるとも思えない。
さて問題は大学の存続を考える時期にあることだ。誰もが「母校」と呼んで同窓会などを通じて生涯大切に思う。しかしその母校が卒業後なくなったらどうするのか、在学中に閉校になったらどうするのか、これから大学に進むものはそうした視点からの進学先の決定が必要になると思われる。決して「どこかで起こる話」ではなく「近くで起こる話」だと認識してほしい。
まず定員に対する充足率だ。掲載した表は公開されている「大学情報公開サイト」から週刊誌「AERA」が発表しているものだが、充足率の高い大学は、ある意味安心ができるかもしれない。充足率143とは募集定員100名に対し143名が入学していることで、驚くべき実績だが、ある意味評価されるべき実績を持っていることである。それらの評価されるべき内容を考察してみると①実習の充実度の高さがあげられる。ことに医療・福祉系ではポイントになると言っていい。外国語系でも同様で、実際に外国語が使え、話せる能力が身につくことに他ならない。②少人数教育の成果である。小規模な文系の大学に目立つ。高校の教員の勧めで進学を決めた学生が半数以上の大学もあることから、こうした教育の内容の充実は、比較的情報も得やすいのではないか。
ただここで忘れてはならないのは入学者の歩留まりの読みが影響する点だ。歩留まりのよくない大学では定員の何倍も合格を発表する。すると時に思いの外歩留まりが高く、学生が定員オーバーしてしまうということだ。評価も高く名も知れた大学が、充足率の高い大学に入らないのはここにある。これらの大学は、多くの合格発表をすれば、歩留まりが高いため、たちまち定員オーバーするほど入学生を迎えることになってしまうからである。ちなみに充足率では112青山学院、111明治、109早稲田、109上智、109同志社、106慶應、102関学など著名な大学、言い換えれば学生を集めやすい大学では、合格発表数を控えるから、充足率は高くはならない。この点も加味して考えたい。
一方充足率の低い学校は、多少合格者を多く発表しても、なお学生を集められない実情にある。充足率30~40%台の大学は、100名募集しているのに30名や40名しか入学してこないという危機的状態に陥っている場合が多い。こうした状態が続けば、他校への吸収合併や、閉校の措置を予想せざるを得ない。こうした大学は圧倒的に地方大学に多く、東京の大学は充足率の低い50大学でも2校しかない。学生の大都市への進学願望を物語っている。東京という都市に対するあこがれである。危険な意識である。いま一つ、短大から4年制へと改組した大学では、短大時代と変わらない指導方針や内容が学生に疎まれる傾向にあることである。これは進学にあたって大いに検討しておくべきことだと思う。
生き残れる大学にはさまざまの要件もあろう。ただ同じ東京都や近郊にあって、なお都心へ移転を試みるいくつもの大学がある。鳴り物入りで郊外へ移転し、それが評価された時代は去り、いまや都心回帰の潮流になりつつある。実際それらの大学は出願数が増え続ける。卒業後も残り続ける大学を見極める、臭覚も眼力も要望される。「家賃2倍でも都心がいい」という学生も多いとか。
文部省の対応にも確かに問題がある。学生減少期がもうそこに見えているのに、毎年毎年新設大学を認め続けた。地方にも大学新設が続いた。目先の学生の進路処理には有効だったかもしれないが、長期的にみれば早くから大学設置数が過剰になることがわかりきっていた。それが今現実に迫ってきている。今度は抑制に転じなければならない。今年文科省は、東京23区内に私大の新設や増員を認めないという対応を決めた。しかしこれが少子化の対応に効果があるとも思えないし、首都圏への学生集中の歯止めになるとも思えない。
さて問題は大学の存続を考える時期にあることだ。誰もが「母校」と呼んで同窓会などを通じて生涯大切に思う。しかしその母校が卒業後なくなったらどうするのか、在学中に閉校になったらどうするのか、これから大学に進むものはそうした視点からの進学先の決定が必要になると思われる。決して「どこかで起こる話」ではなく「近くで起こる話」だと認識してほしい。
まず定員に対する充足率だ。掲載した表は公開されている「大学情報公開サイト」から週刊誌「AERA」が発表しているものだが、充足率の高い大学は、ある意味安心ができるかもしれない。充足率143とは募集定員100名に対し143名が入学していることで、驚くべき実績だが、ある意味評価されるべき実績を持っていることである。それらの評価されるべき内容を考察してみると①実習の充実度の高さがあげられる。ことに医療・福祉系ではポイントになると言っていい。外国語系でも同様で、実際に外国語が使え、話せる能力が身につくことに他ならない。②少人数教育の成果である。小規模な文系の大学に目立つ。高校の教員の勧めで進学を決めた学生が半数以上の大学もあることから、こうした教育の内容の充実は、比較的情報も得やすいのではないか。
ただここで忘れてはならないのは入学者の歩留まりの読みが影響する点だ。歩留まりのよくない大学では定員の何倍も合格を発表する。すると時に思いの外歩留まりが高く、学生が定員オーバーしてしまうということだ。評価も高く名も知れた大学が、充足率の高い大学に入らないのはここにある。これらの大学は、多くの合格発表をすれば、歩留まりが高いため、たちまち定員オーバーするほど入学生を迎えることになってしまうからである。ちなみに充足率では112青山学院、111明治、109早稲田、109上智、109同志社、106慶應、102関学など著名な大学、言い換えれば学生を集めやすい大学では、合格発表数を控えるから、充足率は高くはならない。この点も加味して考えたい。
一方充足率の低い学校は、多少合格者を多く発表しても、なお学生を集められない実情にある。充足率30~40%台の大学は、100名募集しているのに30名や40名しか入学してこないという危機的状態に陥っている場合が多い。こうした状態が続けば、他校への吸収合併や、閉校の措置を予想せざるを得ない。こうした大学は圧倒的に地方大学に多く、東京の大学は充足率の低い50大学でも2校しかない。学生の大都市への進学願望を物語っている。東京という都市に対するあこがれである。危険な意識である。いま一つ、短大から4年制へと改組した大学では、短大時代と変わらない指導方針や内容が学生に疎まれる傾向にあることである。これは進学にあたって大いに検討しておくべきことだと思う。
生き残れる大学にはさまざまの要件もあろう。ただ同じ東京都や近郊にあって、なお都心へ移転を試みるいくつもの大学がある。鳴り物入りで郊外へ移転し、それが評価された時代は去り、いまや都心回帰の潮流になりつつある。実際それらの大学は出願数が増え続ける。卒業後も残り続ける大学を見極める、臭覚も眼力も要望される。「家賃2倍でも都心がいい」という学生も多いとか。