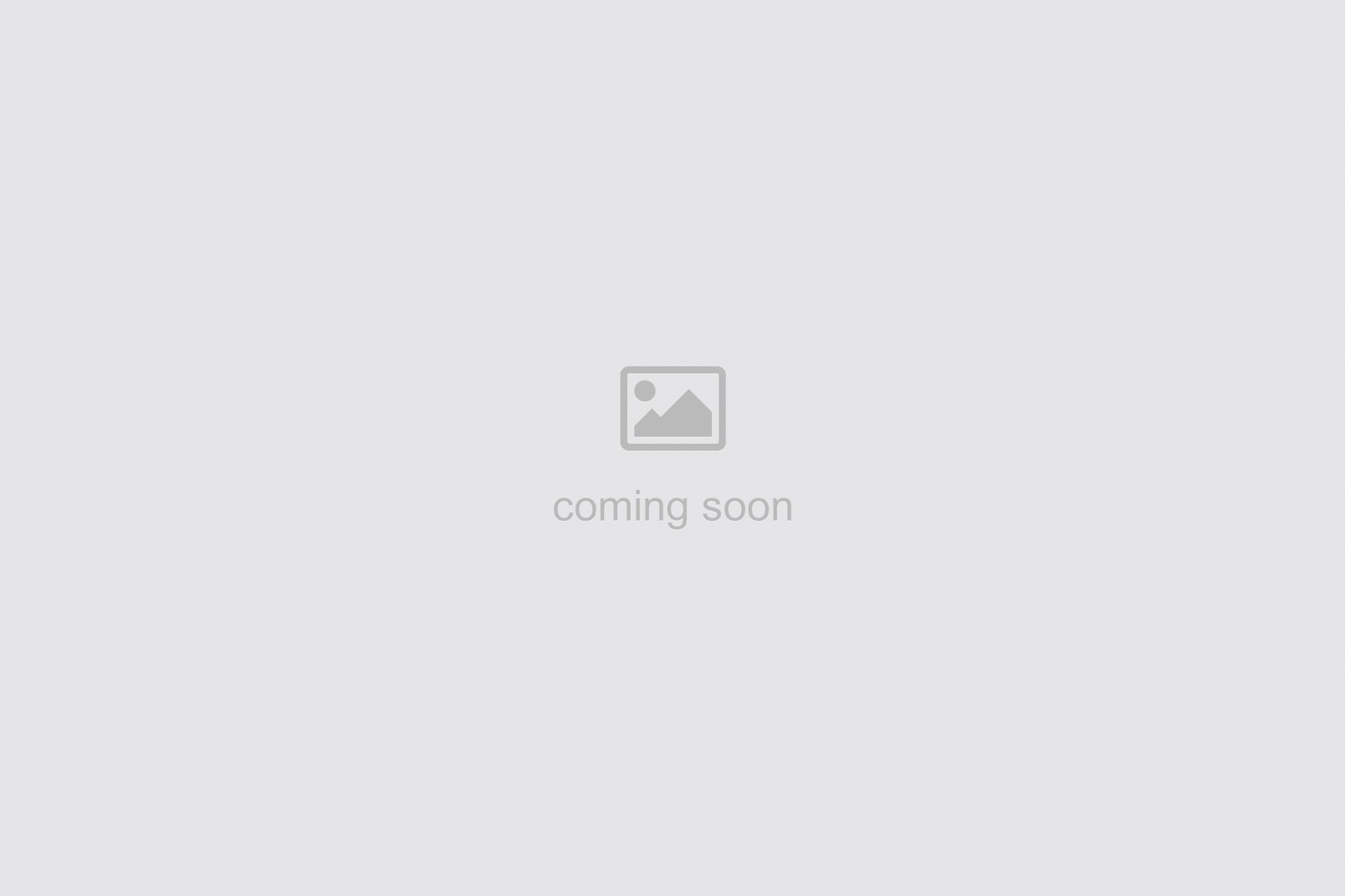新! 学校報「泉」 アーカイブ
若葉学習会学校報「泉」 第693号 (2025年3月号) 今月の職員随想は田口先生
学園ニュース
卒業おめでとう。
先生にまた会いにきてくださいね。
(高校リターン科)
高校リターン科(クラーク記念国際高等学校連携校米子キャンパス)の学年末試験が1月27日~30日に行われました。技能連携科目という商業科の科目はパソコンの実技試験を実施しました。直前の補習日には多くの生徒が試験勉強のためにやってきて、しっかりと練習をしていました。そのかいもあってか、多くの生徒がきちんとできていました。この試験を最後に3年生は自由登校になりました。1年生と2年生だけになり、校舎はさみしくなりましたが、4月からは新入生とまた新しい生活が待っています。楽しみですね。3年生は間もなく卒業式です。クラークでの思い出をいつまでも忘れずに、それぞれの進路で頑張ってください。またこちらに遊びに来てくださいね。
(担当 兼折)
君たち 僕たち①
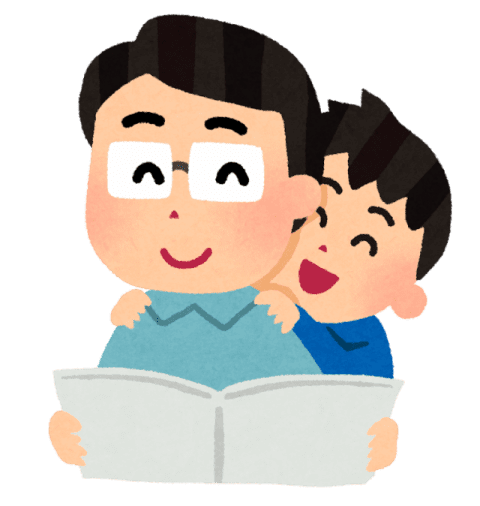
米子校舎 中学1年
藤本 優 さん
藤本 優 さん
6歳の時から2年間、アメリカのオハイオ州に住んでいたという藤本君。せっかく学んだ英語を忘れないようにと、帰国後は自ら英会話教室に通い、日常でも英語で会話する努力を続けてきました。それによって英語力がさらに向上したため、今でも「継続は力なり」という言葉を大切にしていると教えてくれました。彼の次の目標は、英検準1級に合格することです。
また尊敬する人は父親だと話す彼。お父さんとはよく一緒に勉強やテスト直しをするようです。しかしお互いの解答や意見が異なり口論になることもしばしば。それでも最後まで諦めずに、勉強や様々な知識を教えてくれる父であると、嬉しそうに話してくれました。
趣味は音楽を聴くことで、部活は弓道部です。小学1年生の頃からパソコンや電子機器をいじることが好きで、知的好奇心が高かったと振り返っていました。将来はパソコン関係の仕事に就きたいそうです。今後の将来の活躍にとって、彼の好奇心と継続力が大きな武器になることでしょう。
また尊敬する人は父親だと話す彼。お父さんとはよく一緒に勉強やテスト直しをするようです。しかしお互いの解答や意見が異なり口論になることもしばしば。それでも最後まで諦めずに、勉強や様々な知識を教えてくれる父であると、嬉しそうに話してくれました。
趣味は音楽を聴くことで、部活は弓道部です。小学1年生の頃からパソコンや電子機器をいじることが好きで、知的好奇心が高かったと振り返っていました。将来はパソコン関係の仕事に就きたいそうです。今後の将来の活躍にとって、彼の好奇心と継続力が大きな武器になることでしょう。
(担当 松重)
君たち 僕たち②
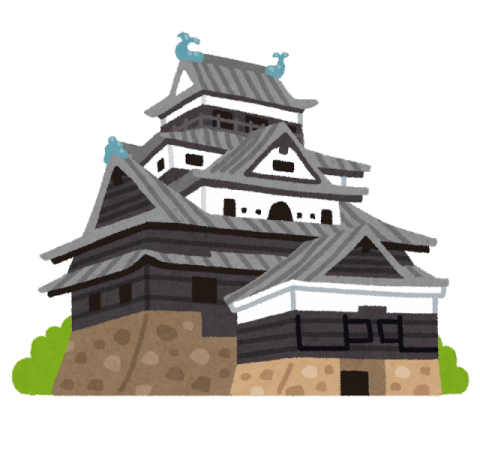
米子校舎 高校3年
須山 桜さん
西釋 ももこさん
多様化の時代、大学入試も種々様々。ただし共通テスト前に国立大学の合格を得られるのは稀です。島根大学独自のシステム「へるん入試」で早々と合格を勝ち取ったのがこの二人の米東生です。
二人は揃って教育学部で小学校教諭を目指します。母校西伯小学校の地域と密着した教育を理想的教育と考える須山さん。特別支援学校で個々の児童に向けた教育を実践なさるお父様に感化された西釋さん。恵まれた環境に裏打ちされた立派な将来展望です。
実家から松江に通う予定の須山さん。同じ大学学部に実家から通っているお姉様が大学とバイトを両立している姿に憧れているようです。
松江に部屋を借りる西釋さん。元来独り時間を大切にしたいタイプだそうで、最近始めた編み物や料理を満喫したいと独り暮らしが楽しみで仕方がないようです。
明るく物怖じせず堂々と話すことができる二人。就活生の話を聞くと今社会が求めているのはこんな人材だと感じます。須山先生、西釋先生になったらまた会いましょう。
(担当 門脇)
西釋 ももこさん
多様化の時代、大学入試も種々様々。ただし共通テスト前に国立大学の合格を得られるのは稀です。島根大学独自のシステム「へるん入試」で早々と合格を勝ち取ったのがこの二人の米東生です。
二人は揃って教育学部で小学校教諭を目指します。母校西伯小学校の地域と密着した教育を理想的教育と考える須山さん。特別支援学校で個々の児童に向けた教育を実践なさるお父様に感化された西釋さん。恵まれた環境に裏打ちされた立派な将来展望です。
実家から松江に通う予定の須山さん。同じ大学学部に実家から通っているお姉様が大学とバイトを両立している姿に憧れているようです。
松江に部屋を借りる西釋さん。元来独り時間を大切にしたいタイプだそうで、最近始めた編み物や料理を満喫したいと独り暮らしが楽しみで仕方がないようです。
明るく物怖じせず堂々と話すことができる二人。就活生の話を聞くと今社会が求めているのはこんな人材だと感じます。須山先生、西釋先生になったらまた会いましょう。
(担当 門脇)
(世界遺産シリーズ) 紀伊山地の霊場と参詣道 日本

卒業生はいま

筑波大学 物理学類
上本 凰加 さん
上本 凰加 さん
今回は中1から中3まで倉吉校舎に通学した上本凰加くんを紹介します。現在は情報系を学習していて興味を持っている彼。中学の頃もいろいろなことに興味関心を持ち、勉強が好きだった生徒でした。勉強が好きという面では、私の教え子の中でも一番です。
大学では現代視覚文化研究会に所属して代表を務めているとのこと。とても充実した日々を過ごしているようです。
そんな彼が現在しているアルバイトがなんと塾講師なのです。「先生、僕生徒の名前を覚えるのが苦手で…」塾の様子などいろいろ教えてもらいました。「凰加くん、初対面の生徒でも絶対名前を覚えることは大切!それがコミュニケーションの第一歩だよ。」と私からのアドバイス。彼自身、このバイトを通して、人と関わることの大切さを学んだと熱く語ってくれました。
将来はまだ決まっていないとのこと。ただ、いろんなことがやりたいと目を輝かせながら話す彼の表情は印象的でした。彼ならどんな分野へ進んでも、あらゆる能力を発揮してくれるにちがいありません。
来月若葉では新年度に向け「体験入学」が開催されます。彼にアドバイスしたことを私自身、肝に銘じて、体験入学に臨みます。「~さん、こんにちは。今日は一緒にがんばろうね。」凰加くんが初めて若葉へ来た時もそう接した記憶があります。あれから八年、変わらない姿勢で臨むことを彼への取材を通して再認識しました。
大学では現代視覚文化研究会に所属して代表を務めているとのこと。とても充実した日々を過ごしているようです。
そんな彼が現在しているアルバイトがなんと塾講師なのです。「先生、僕生徒の名前を覚えるのが苦手で…」塾の様子などいろいろ教えてもらいました。「凰加くん、初対面の生徒でも絶対名前を覚えることは大切!それがコミュニケーションの第一歩だよ。」と私からのアドバイス。彼自身、このバイトを通して、人と関わることの大切さを学んだと熱く語ってくれました。
将来はまだ決まっていないとのこと。ただ、いろんなことがやりたいと目を輝かせながら話す彼の表情は印象的でした。彼ならどんな分野へ進んでも、あらゆる能力を発揮してくれるにちがいありません。
来月若葉では新年度に向け「体験入学」が開催されます。彼にアドバイスしたことを私自身、肝に銘じて、体験入学に臨みます。「~さん、こんにちは。今日は一緒にがんばろうね。」凰加くんが初めて若葉へ来た時もそう接した記憶があります。あれから八年、変わらない姿勢で臨むことを彼への取材を通して再認識しました。
(担当 濱)
職員随想
退職後の農業挑戦
田口 進
高齢者と言われるのは何歳からでしょうか。日本の企業で60歳を定年としている割合は約80%、65歳を定年としている割合は約20%だそうです。現在の日本の企業では65歳までの「雇用確保措置の実施」が義務づけられ2021年4月から新たに、70歳までの「就業機会の確保」が努力義務として課せられるようになったようです。まだまだ、体力があり健康に働くことができるうちは本人の希望に応じて働く機会を提供する、若い世代を育てるためにも必要な人材である。というのが国の考え方のようです。
65歳以上の男女の健康状態は、日常生活に影響がある人は約4分の1だそうです。若いころと比べて体力に変化や不安はありながらも、比較的健康に暮らしている人が多いと言えます。
定年後「働くこと」がなくなり、生きがいを失ってしまう人も少なくないと言われます。趣味もなく、退屈になってしまい、家に閉じこもりになって体力が落ちてしまうこともあります。しかし、60代はまだまだ体力があり、家のことなど色んなことができると思い、私も親から受け継いだ耕作地を利用して農業に挑戦しています。始めたばかりですが、かなり大変だということが分かりました。兼業農家として農業を行っているほどではないですが、自分が食べたいものを栽培でき、自然に触れながら体を動かすことで本業の息抜きになるだけでなく、趣味的なかかわりなので、精神的な余裕も生まれます。そして、できた作物を市場などに販売することもできます。
一般的に農業は、肉体労働が多く日々の作業による負担は大きいと思います。特に高齢者や病気になった時、農業の仕事を続けるのが難しくなります。機械化が進んでいるものの、体力の必要な作業が多いため、体がついていかないことが原因で農業をやめることもあります。
現在私が住んでいる境港市の農地(水田)は、湿田が多くまた水田面積が小さいため、担い手となる稲作農家はおらず、農業者の高齢化・労働力不足などにより、耕作放棄地・不作付地の拡大が大きな問題となっているようです。畑についても同じ状況で、私の耕作地のまわりにも耕作放棄地になっているところが目立ってきています。
農業の魅力は、自然とともに生活することだとよく言われたりします。農業で働く人の生活は、朝早くから始まり、日が暮れてから終わるという規則正しいリズムを持っています。その生活の中で、雨の量や雲の動き、動物など、日々さまざまな発見があります。もちろん大変さも伴いますが、自然が好きだという人にとっては、農業はとても魅力的な職業かもしれません。
また、「努力が形になりやすい」のも農業です。例えば、大きな畑を耕せば耕すほど収穫も増え、その結果として得られる収入も増えます。作業が増えるとともに困難も増えますが、その困難を乗り越えた結果がわかりやすく現れることも農業の大きな魅力の一つだと思います。結果が見えやすい、分かりやすいことは、モチベーションを保つうえでの重要な要素だと思います。
現在、私が栽培している作物は、初心者ですので、にんにく、玉ねぎ、イチゴ、大根、サツマイモなど、比較的手がかからない物を栽培しています。ニンニクは黒ニンニクにしたり、サツマイモは干し芋にしたりして楽しんでいます。栽培にはいろいろな失敗はありますが、日々挑戦していきたいと思います。
65歳以上の男女の健康状態は、日常生活に影響がある人は約4分の1だそうです。若いころと比べて体力に変化や不安はありながらも、比較的健康に暮らしている人が多いと言えます。
定年後「働くこと」がなくなり、生きがいを失ってしまう人も少なくないと言われます。趣味もなく、退屈になってしまい、家に閉じこもりになって体力が落ちてしまうこともあります。しかし、60代はまだまだ体力があり、家のことなど色んなことができると思い、私も親から受け継いだ耕作地を利用して農業に挑戦しています。始めたばかりですが、かなり大変だということが分かりました。兼業農家として農業を行っているほどではないですが、自分が食べたいものを栽培でき、自然に触れながら体を動かすことで本業の息抜きになるだけでなく、趣味的なかかわりなので、精神的な余裕も生まれます。そして、できた作物を市場などに販売することもできます。
一般的に農業は、肉体労働が多く日々の作業による負担は大きいと思います。特に高齢者や病気になった時、農業の仕事を続けるのが難しくなります。機械化が進んでいるものの、体力の必要な作業が多いため、体がついていかないことが原因で農業をやめることもあります。
現在私が住んでいる境港市の農地(水田)は、湿田が多くまた水田面積が小さいため、担い手となる稲作農家はおらず、農業者の高齢化・労働力不足などにより、耕作放棄地・不作付地の拡大が大きな問題となっているようです。畑についても同じ状況で、私の耕作地のまわりにも耕作放棄地になっているところが目立ってきています。
農業の魅力は、自然とともに生活することだとよく言われたりします。農業で働く人の生活は、朝早くから始まり、日が暮れてから終わるという規則正しいリズムを持っています。その生活の中で、雨の量や雲の動き、動物など、日々さまざまな発見があります。もちろん大変さも伴いますが、自然が好きだという人にとっては、農業はとても魅力的な職業かもしれません。
また、「努力が形になりやすい」のも農業です。例えば、大きな畑を耕せば耕すほど収穫も増え、その結果として得られる収入も増えます。作業が増えるとともに困難も増えますが、その困難を乗り越えた結果がわかりやすく現れることも農業の大きな魅力の一つだと思います。結果が見えやすい、分かりやすいことは、モチベーションを保つうえでの重要な要素だと思います。
現在、私が栽培している作物は、初心者ですので、にんにく、玉ねぎ、イチゴ、大根、サツマイモなど、比較的手がかからない物を栽培しています。ニンニクは黒ニンニクにしたり、サツマイモは干し芋にしたりして楽しんでいます。栽培にはいろいろな失敗はありますが、日々挑戦していきたいと思います。