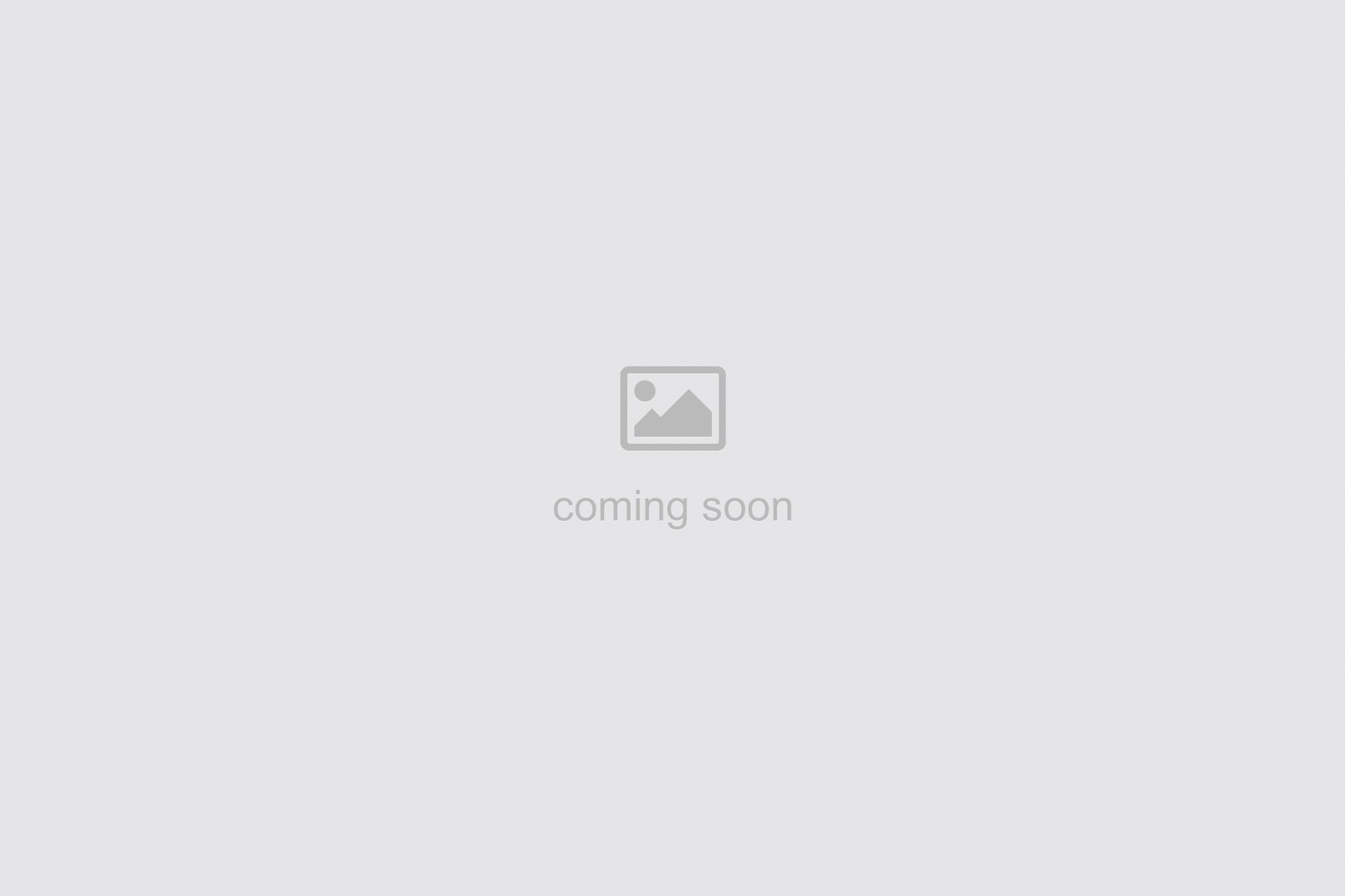新! 学校報「泉」 アーカイブ
若葉学習会学校報「泉」 第690号 (2024年12月号) 今月の職員随想は古徳先生
学園ニュース
秋が深くなりました。
今月の一コマです。
(米子校舎)
◆10月20日(日)は第2回統一模試の実施日でした。米子会場は米子松蔭高校。高校が会場になるとやはり模試の緊張感が上がる気がします。廊下がとても長く、実施本部と教室の往復で試験監督である記者のスマホの万歩計は一万歩超え!もう成績は返却済み。最終回に向けて、復習を怠りなく。
◆これはある日の夕刻、1号館入り口から撮った空の写真です。秋の夕焼けは本当に綺麗です。自習室で勉強をしている受験生。突然不安に襲われたり、どうしても集中できなかったり、そんな日もありますよね。そんな時には少し散歩をしてみるのはどうでしょう。夕焼けに限らず風景に新たな発見があって、ストレスを少し発散できるかもしれません。
(担当 吉野)
(担当 吉野)
君たち 僕たち①

米子校舎 中学3年
斉木 宗太郎 さん
斉木 宗太郎 さん
「将来はリーダー的な存在となって、みんなを引っぱっていくような仕事をしたい」柔らかな人当たりとの間にギャップを感じましたが、彼のそんな将来像が垣間見えたのが中学3年生時の体育祭についての話でした。ダンスなどみんなで協力してやることが好きで、そういった活動で得られる人と関われたという感覚が大きな充実感に繋がっているそうです。
いとこの影響で小学3年生の時に始めた野球を中学3年まで継続中。中学のチームではキャッチャーとして活躍しました。若葉での他中学の友達は野球を通じた縁がきっかけだそうですが、そのコミュニケーション力の高さには人と関わりたいという彼の基本的なスタンスも少なからず影響しているのでしょう。
高校に入ってやりたいことをたずねた時の返答にもそれが表れます。「小中時代はずっと同じ地域の同じメンバーの中での関わりだったので、高校では新しい友達をつくりたい」様々に揺れるのが普通であるこの年代で、この一貫性は立派ですね。
(担当 吉野)
いとこの影響で小学3年生の時に始めた野球を中学3年まで継続中。中学のチームではキャッチャーとして活躍しました。若葉での他中学の友達は野球を通じた縁がきっかけだそうですが、そのコミュニケーション力の高さには人と関わりたいという彼の基本的なスタンスも少なからず影響しているのでしょう。
高校に入ってやりたいことをたずねた時の返答にもそれが表れます。「小中時代はずっと同じ地域の同じメンバーの中での関わりだったので、高校では新しい友達をつくりたい」様々に揺れるのが普通であるこの年代で、この一貫性は立派ですね。
(担当 吉野)
君たち 僕たち②

高校リターン科1年
守 統哉 さん
今回紹介する守統哉(もりとうや)さんは、この10月に本校に転校して来ました。すらっとした男子で、何かスポーツをやっていたのかなと思いましたが、スポーツの方はサッカーの観戦が趣味というだけで、前の学校では中学校時代に文化祭で劇の主役を務めたことから興味を持った演劇部に所属していたそうです。6月には鳥取県の西部地区大会にも参加しています。
一般の演劇では、子供の役は子供が、大人の役は大人が演じますが、高校演劇では、当然すべての役を高校生が演じなければなりません。これが高校演劇の魅力の一つで、演じようとする役について深い理解が求められます。彼が日頃から心がけていることは、相手の立場に立って考えることだそうです。演劇部は文科系ですが、体づくりのためランニングや柔軟と勿論発声練習が必要で、きつかったけれど達成感を得ることが出来たそうです。
まだ将来の夢は見つかっていませんが、少しずつ自分に合ったものを探していきたいと語る彼でした。
(担当 河田)
今回紹介する守統哉(もりとうや)さんは、この10月に本校に転校して来ました。すらっとした男子で、何かスポーツをやっていたのかなと思いましたが、スポーツの方はサッカーの観戦が趣味というだけで、前の学校では中学校時代に文化祭で劇の主役を務めたことから興味を持った演劇部に所属していたそうです。6月には鳥取県の西部地区大会にも参加しています。
一般の演劇では、子供の役は子供が、大人の役は大人が演じますが、高校演劇では、当然すべての役を高校生が演じなければなりません。これが高校演劇の魅力の一つで、演じようとする役について深い理解が求められます。彼が日頃から心がけていることは、相手の立場に立って考えることだそうです。演劇部は文科系ですが、体づくりのためランニングや柔軟と勿論発声練習が必要で、きつかったけれど達成感を得ることが出来たそうです。
まだ将来の夢は見つかっていませんが、少しずつ自分に合ったものを探していきたいと語る彼でした。
(担当 河田)
(世界遺産シリーズ) 冬の岐阜県・白川郷のライトアップ 日本

卒業生はいま

鳥取県職員
岡田 あすか さん
長谷川 美雛 さん
岡田 あすか さん
長谷川 美雛 さん
私は高校生によく「今の友達が生涯の友達になることは稀だ。頑張って大学に合格して最良の友達に出会おう!」と話す。ただ、この二人はどう考えても生涯の友達になりそうだ。
同じ幼稚園に通った二人は中学生の時に若葉で再会し、米子東高校のテニス部で意気投合。そろって島根大学に進学し、バイトに遊びに共に過ごす時間は増大した。そして今年の春、二人そろって鳥取県職員に採用されたのだ。
進学も就職も二人で相談したわけではなく、たまたまだという。勤務地は鳥取市と倉吉市と離れているが、大多数の週末を一緒に過ごしている。この度も、取材依頼を快諾してくれた二人は、週末にそろって米子に帰ってきてくれた。
鳥取県庁で総務担当として行政事務の仕事をしている岡田さん。中部総合事務所で農業職の改善普及員として働く長谷川さん。二人とも大学時代に身につけたスキルを活かし、就職一年目ながらバリバリ働いているようだ。
性格は対照的で、お互いにないところを補い合ういいバランスの関係だという。「美雛は安心感!周りを本当に大切にする人間です」と岡田さん。「あすかは聞き上手!どんな悩みもポジティブに変換してくれます」と長谷川さん。悩みがちな社会人一年目を二人が大いに楽しめている要因は、まぎれもなく親友の存在だ。
「頑張った分だけ、きっと楽しいことが待っていますよ!」と岡田さん。「勉強だけでなく遊びにも全力投球してください!」と長谷川さん。生徒諸君!何事も頑張って楽しい人生を目指そうよ、この二人のように!
同じ幼稚園に通った二人は中学生の時に若葉で再会し、米子東高校のテニス部で意気投合。そろって島根大学に進学し、バイトに遊びに共に過ごす時間は増大した。そして今年の春、二人そろって鳥取県職員に採用されたのだ。
進学も就職も二人で相談したわけではなく、たまたまだという。勤務地は鳥取市と倉吉市と離れているが、大多数の週末を一緒に過ごしている。この度も、取材依頼を快諾してくれた二人は、週末にそろって米子に帰ってきてくれた。
鳥取県庁で総務担当として行政事務の仕事をしている岡田さん。中部総合事務所で農業職の改善普及員として働く長谷川さん。二人とも大学時代に身につけたスキルを活かし、就職一年目ながらバリバリ働いているようだ。
性格は対照的で、お互いにないところを補い合ういいバランスの関係だという。「美雛は安心感!周りを本当に大切にする人間です」と岡田さん。「あすかは聞き上手!どんな悩みもポジティブに変換してくれます」と長谷川さん。悩みがちな社会人一年目を二人が大いに楽しめている要因は、まぎれもなく親友の存在だ。
「頑張った分だけ、きっと楽しいことが待っていますよ!」と岡田さん。「勉強だけでなく遊びにも全力投球してください!」と長谷川さん。生徒諸君!何事も頑張って楽しい人生を目指そうよ、この二人のように!
(担当 門脇)
職員随想
今の社会に関心を
古徳 知浩
先月の一日に臨時国会が召集され、自民党の新総裁が、第一〇二代首相に選出された。鳥取県としては初めての内閣総理大臣ということもあり、県内ではお祭り騒ぎとなった。こういった経緯で、授業中に、「現在の総理大臣の名前は?」という質問をしたところ、誰からも「石破茂」という解答が出てこなかったのは衝撃であった。
中国地方で見てみると、お隣の島根県では、消費税の導入をした「竹下登」、岡山県では五・一五事件で有名な「犬養毅」、広島県では増税メガネで知名度を上げた「岸田文雄」が挙げられる。山口県に至っては、初代内閣総理大臣の「伊藤博文」やノーベル平和賞を受賞した「佐藤栄作」、アベノミクスやモリカケ問題で記憶に新しい「安倍晋三」など総理大臣輩出の宝庫である。
この長い歴史の中、ようやく鳥取県から総理大臣が誕生したというのに、ほとんどの中学生たちが興味を持っていないことに驚いた。しかし、ふと冷静に考えて見ると、自分が若い頃に政治や経済に興味を持っていたかと聞かれたら、答えは「ノー」だ(笑)。自分のことを棚に上げて、今の中学生たちを批判するつもりは毛頭ない。ただ私が思うに、教育の仕方を変えていけば、子どもたちにも政治に関心を持たせ、将来的には国政選挙の投票率も上昇させることができるのではないかと思っている。
歴史の授業をする際に、ほぼ例外なく古代から順に中世、近世、近代、現代という古い順に展開されていく。歴史的な出来事の背景や因果関係を理解しやすくするために、時系列順に教えるのが一般的である。これはとても理にかなっていると思う。また、歴史を学ぶ目的は、過去の社会的な仕組みや戦争などの愚かな失敗を理解することで、新たな知恵を出し、現代の社会に反映させ、改善していくことにある。
ところが、古代や中世の記載内容があまりに多いため、近代や現代(公民)を丁寧に説明する時間がないのが現状だ。年間に教えられる時間数には、どうしても限界がある。繰り返すが、前述したように過去を学び、今に活かすことこそ歴史を学ぶ意義がある。それなのに現代の内容が疎かになることが、とても残念でならない。
奈良時代の頃の「租・調・庸」といった昔の税制度ももちろん大切だが、現在の「103万円の壁」や「年金保険」などの仕組みを、時間をかけて指導する方が有意義だと私は思う。むしろ、現在の税や社会保障制度を知らないというのは、本末転倒である。今の仕組みを知れば、それを作成している官僚や政治家、政党にも注目し、選挙にも意欲を持つはずだ。
バブル崩壊の90年代から現在に至るまでの「失われた30年」の間に、消費税は3回も増税されてきた。不景気のときには減税をすると教科書には書いてあるにも関わらず、実際には増税しかしていないのが今の日本である。社会保険料も同時に上がっているので、給料の手取りは一向に増える様子がない。大阪万博やODA(政府開発援助)などにはすぐに予算を出すくせに、国民への減税に対しては腰が重いのだ。こういったことに疑問を持ち、中学生の頃から前向きに勉強していって欲しいと思う。
社会という教科を学ぶ際に、古代や中世の内容を少し軽くし、現代(公民)に比重を置くことがあってもいいのではないか。このような考えに賛否が出てくることは当然であるが、ぜひこの話題で、みんなと激論を交わしたい。
中国地方で見てみると、お隣の島根県では、消費税の導入をした「竹下登」、岡山県では五・一五事件で有名な「犬養毅」、広島県では増税メガネで知名度を上げた「岸田文雄」が挙げられる。山口県に至っては、初代内閣総理大臣の「伊藤博文」やノーベル平和賞を受賞した「佐藤栄作」、アベノミクスやモリカケ問題で記憶に新しい「安倍晋三」など総理大臣輩出の宝庫である。
この長い歴史の中、ようやく鳥取県から総理大臣が誕生したというのに、ほとんどの中学生たちが興味を持っていないことに驚いた。しかし、ふと冷静に考えて見ると、自分が若い頃に政治や経済に興味を持っていたかと聞かれたら、答えは「ノー」だ(笑)。自分のことを棚に上げて、今の中学生たちを批判するつもりは毛頭ない。ただ私が思うに、教育の仕方を変えていけば、子どもたちにも政治に関心を持たせ、将来的には国政選挙の投票率も上昇させることができるのではないかと思っている。
歴史の授業をする際に、ほぼ例外なく古代から順に中世、近世、近代、現代という古い順に展開されていく。歴史的な出来事の背景や因果関係を理解しやすくするために、時系列順に教えるのが一般的である。これはとても理にかなっていると思う。また、歴史を学ぶ目的は、過去の社会的な仕組みや戦争などの愚かな失敗を理解することで、新たな知恵を出し、現代の社会に反映させ、改善していくことにある。
ところが、古代や中世の記載内容があまりに多いため、近代や現代(公民)を丁寧に説明する時間がないのが現状だ。年間に教えられる時間数には、どうしても限界がある。繰り返すが、前述したように過去を学び、今に活かすことこそ歴史を学ぶ意義がある。それなのに現代の内容が疎かになることが、とても残念でならない。
奈良時代の頃の「租・調・庸」といった昔の税制度ももちろん大切だが、現在の「103万円の壁」や「年金保険」などの仕組みを、時間をかけて指導する方が有意義だと私は思う。むしろ、現在の税や社会保障制度を知らないというのは、本末転倒である。今の仕組みを知れば、それを作成している官僚や政治家、政党にも注目し、選挙にも意欲を持つはずだ。
バブル崩壊の90年代から現在に至るまでの「失われた30年」の間に、消費税は3回も増税されてきた。不景気のときには減税をすると教科書には書いてあるにも関わらず、実際には増税しかしていないのが今の日本である。社会保険料も同時に上がっているので、給料の手取りは一向に増える様子がない。大阪万博やODA(政府開発援助)などにはすぐに予算を出すくせに、国民への減税に対しては腰が重いのだ。こういったことに疑問を持ち、中学生の頃から前向きに勉強していって欲しいと思う。
社会という教科を学ぶ際に、古代や中世の内容を少し軽くし、現代(公民)に比重を置くことがあってもいいのではないか。このような考えに賛否が出てくることは当然であるが、ぜひこの話題で、みんなと激論を交わしたい。